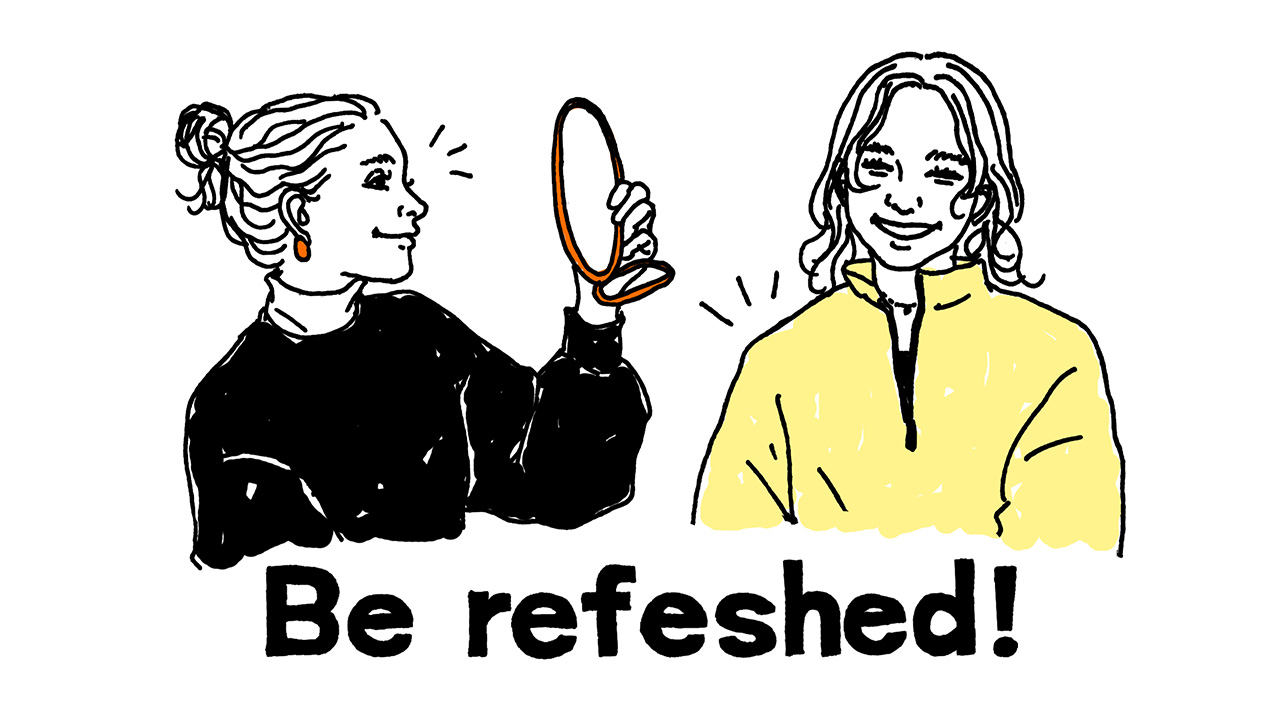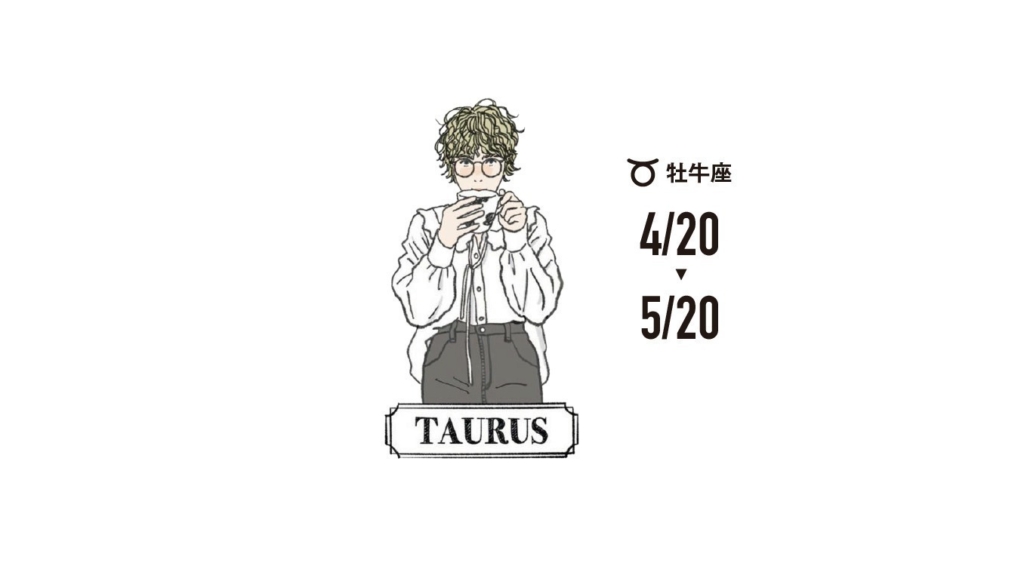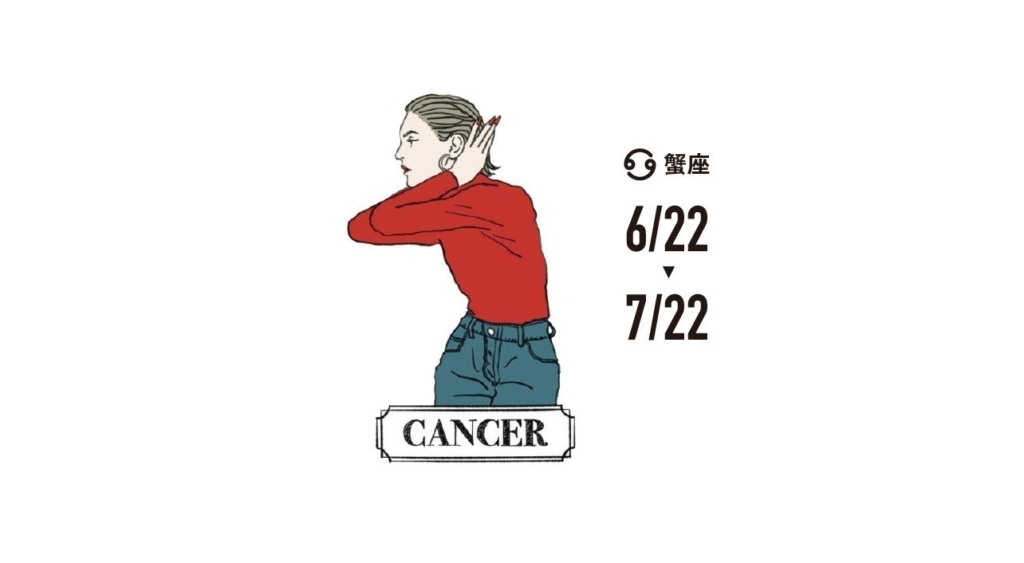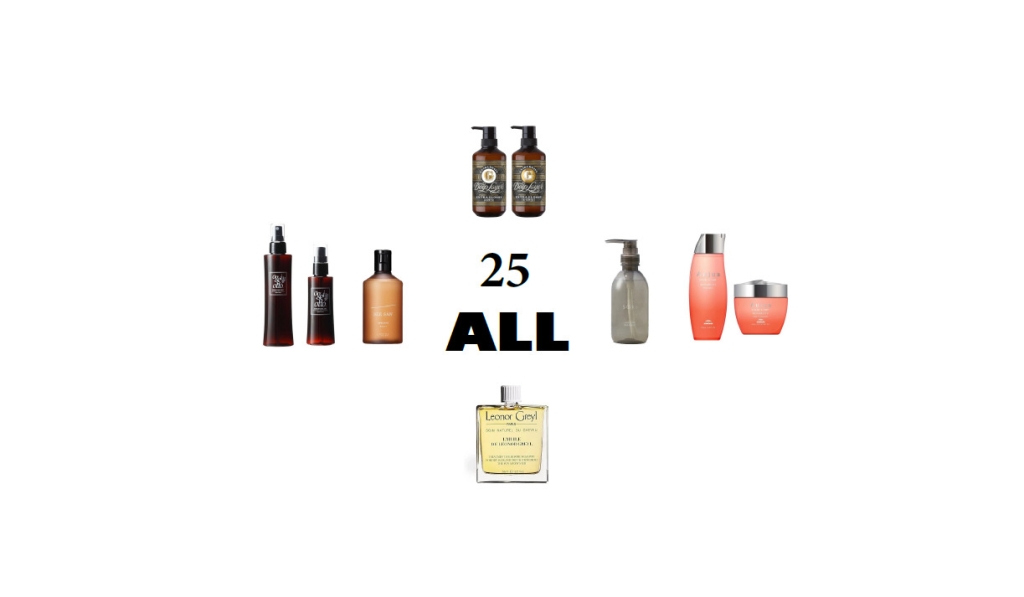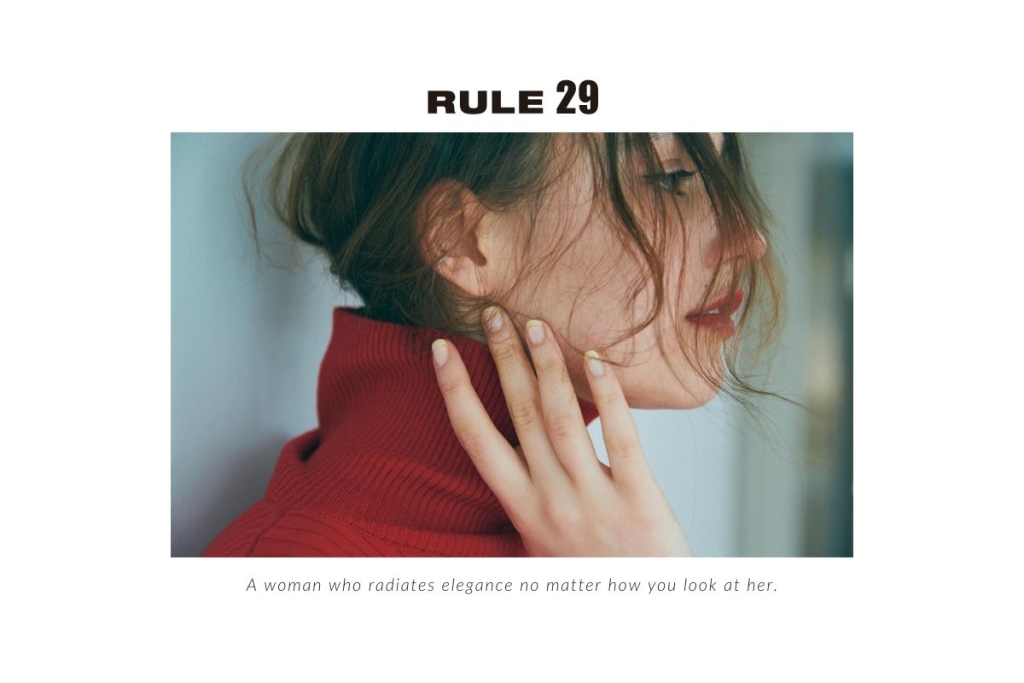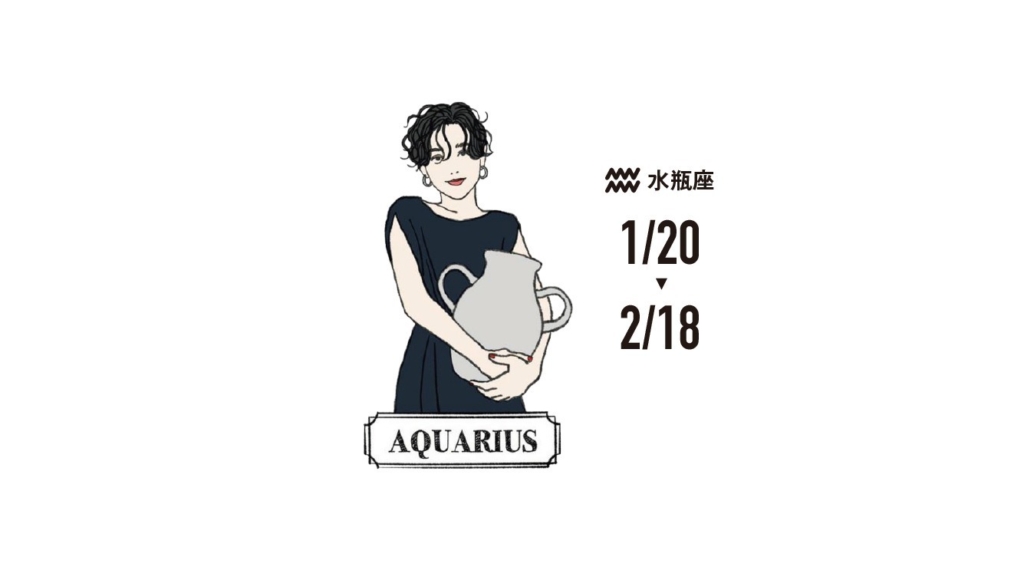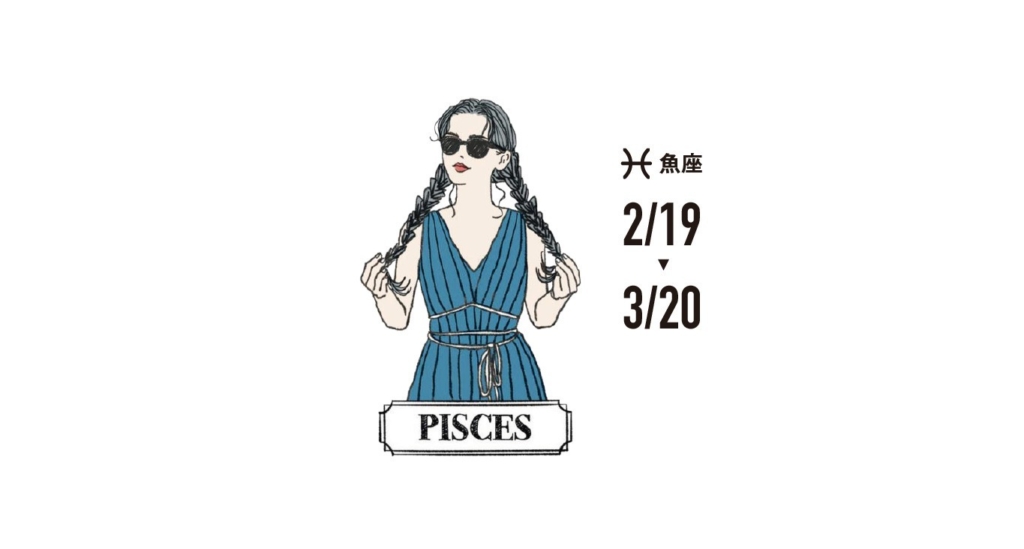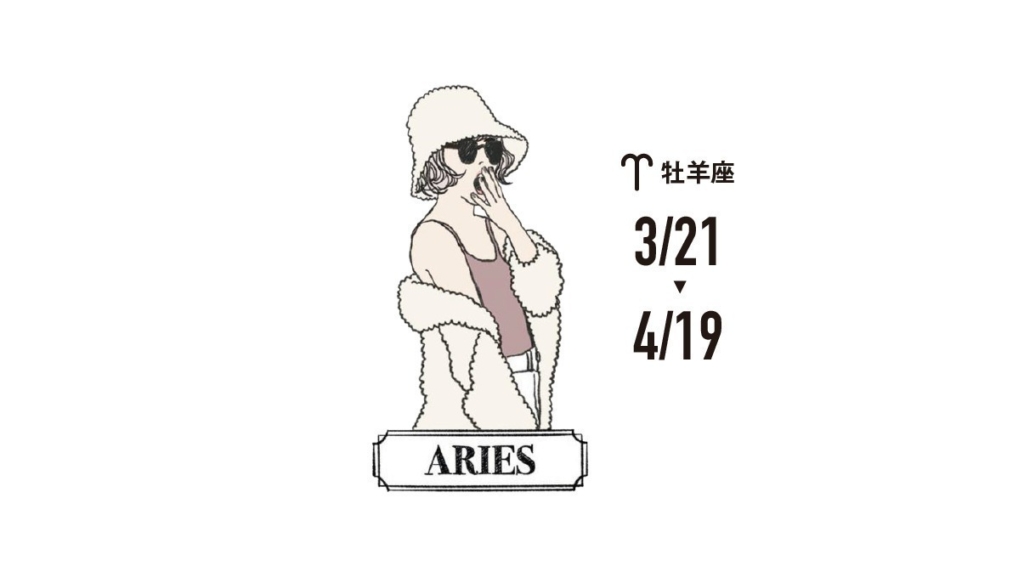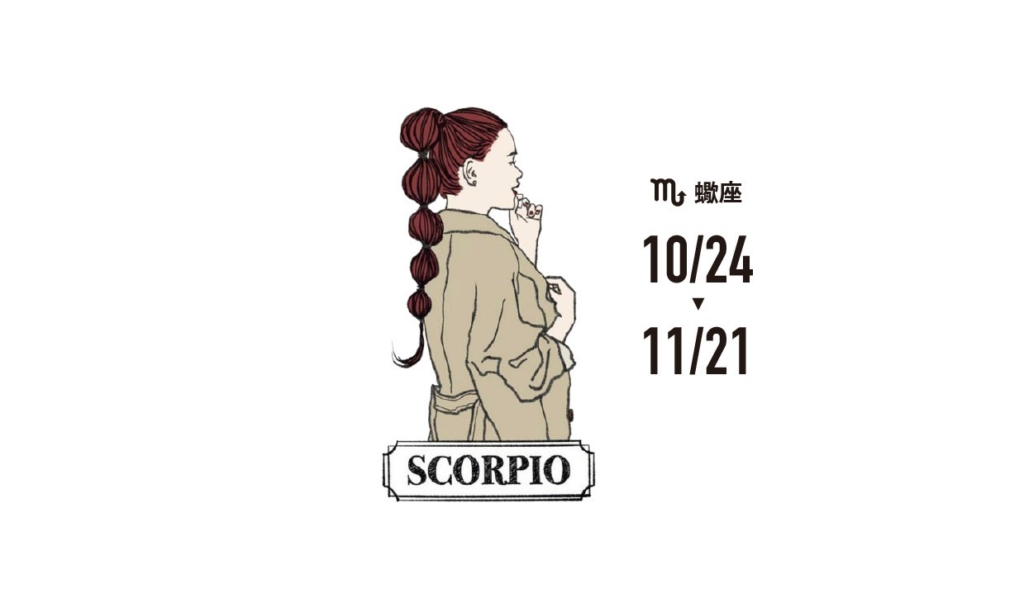顔のたるみに大きく関係 「骨委縮」とは?
頬のたるみ、目の周りのくぼみ、ぼやけたフェイスライン…。加齢とともに現れてくる悩み、その原因は肌ではなく、その土台である「顔の骨」も大きく関係してきます。あなたの顔からその若々しさを奪っていく「骨委縮」。その進行を遅らせるための、具体的な予防策をご紹介。
(※本記事の内容は医学的研究に基づく一般的な傾向を示したものであり、顔のたるみには皮膚の弾力低下、筋肉の衰え、脂肪の減少など複数の要因が複合的に作用し、骨委縮の進行や顔への影響には個人差があります。気になる症状がある場合は専門医にご相談ください)
「顔の骨が委縮」で起こる変化
美容医療の専門誌『Aesthetic Surgery Journal』に掲載された研究でも、加齢とともに眼窩(目の周りの骨)や上顎骨が萎縮し、これが目の下のくぼみやたるみの原因になることが報告されています。

「骨萎縮」とは、加齢とともに骨の密度が低下し、痩せ細っていく現象。顔の骨も例外ではなく特に、目の周り、頬、口元の骨は加齢の影響を受けやすく、骨が痩せることで顔の「土台」が崩れ、皮膚や脂肪を支えきれなくなる。これがたるみを引き起こす大きな原因。
例えるなら、まるで家の基礎が腐食して、壁が崩れ落ちてしまうようなもの。どんなに外壁を塗り直しても、基礎が脆いままでは家全体が傾いてしまうのと同じ現象。
目の周りのくぼみと疲れた印象

目の周りの骨が痩せると、眼球を支えきれなくなり、まぶたの上がくぼんだり、目の下に影ができやすく。これにより、どんなに睡眠をとっても消えない「クマ」や「疲労感」が定着し、実年齢以上に老けて見えてしまうというという結果を招いてしまうのです。
口元の「への字」と寂しい印象
口周りの骨(上顎骨や下顎骨)が痩せると、口角を支える筋肉も衰えやすくなり、口元が「への字」に。怒っているわけでもないのに不機嫌に見えたり、口元のボリュームが失われ、顔全体が寂しい印象に。
ぼやけたフェイスラインと平坦な顔
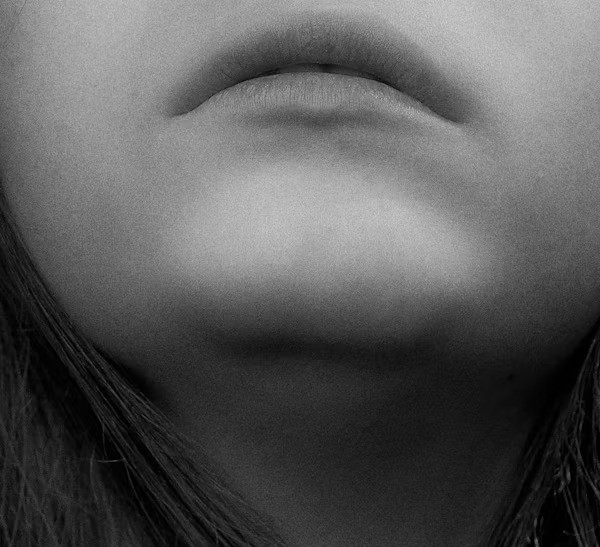
頬骨や顎の骨が痩せることで、顔全体の輪郭が曖昧になり、シャープな印象から遠ざかってしまう。これにより、顔がのっぺりとした平坦な印象になり、メイクで立体感を出すことすら難しくなっていく…という結果に。
「たるまない土台」を作るための鉄則
骨萎縮によるたるみは、今すぐ対策を始めることで進行を遅らせることが可能。ここでは、研究機関でも効果が実証されている、具体的な3つの習慣をご紹介。
【鉄則①】
カルシウムは「ビタミンD」とセットで摂取する
骨の健康にカルシウムが不可欠なのは誰もが知るところ。ですがその吸収率には重大な落とし穴が。カルシウムは、腸からの吸収を助けるビタミンDとセットでなければ、十分に骨に取り込まれません。

2016年に日本骨粗鬆症学会が発表した「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」でも、高齢女性の骨折リスクを低減するためには、カルシウムだけでなくビタミンDの摂取が重要であることが示されました。
①ビタミンDが豊富な食品を積極的に摂取する
(例)鮭、キノコ類(特にキクラゲやしいたけ)卵黄など
②適度に日光を浴びること
短時間(10〜15分程度)の日光浴でビタミンDは生成されますが、日焼け止めを塗るとビタミンDの生成効率は大幅に低下。紫外線の中でも、ビタミンD生成に必要なのは「UVB」という波長。日焼け止めの多くは、このUVBをカットする機能が非常に高く、日焼け止めを塗った状態での短時間の日光浴では、ビタミンDの生成は期待できない、というのが専門家の間での共通認識。
「手のひら日光浴」という選択肢
顔や体に日焼け止めを塗った状態で、手のひらや足の甲など、日焼けによるシミや肌老化が比較的気になりにくい部位を10〜15分程度、太陽に当てる方法。これは、日焼け止めを塗らないことで必要なUVBを効率よく吸収し、体全体にビタミンDを行き渡らせることを目的としたもの。
必要な日光浴時間の目安は?
季節や地域、時間帯によって必要な時間は異なります。例えば、独立行政法人国立環境研究所が公開しているデータによると、7月のつくば市で正午頃に顔と手の甲を露出し、1日に必要なビタミンDを生成するのに必要な時間は約3.5分というシミュレーション結果。一方で、12月の札幌では、同じ量のビタミンDを生成するのに約76分かかるとされており、季節や場所によって大幅に変動することがわかっています。
【鉄則②】
骨の新陳代謝を促す「ビタミンK2」に注目する
2015年に『Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons』に掲載されたメタアナリシス(複数の研究を統合して分析する手法)では、ビタミンK2の補給が骨密度の維持に効果的であると結論づけられています。

ビタミンK2は、骨にカルシウムを定着させる働きを持つ重要な栄養素。単にカルシウムを摂るだけでなく、そのカルシウムを「骨に運んでくれる」役割を担います。
実際、最近の研究では、ビタミンKが不足すると、カルシウムが骨ではなく血管などの不適切な場所に沈着するリスクが高まることがわかっています。推奨するのはビタミンK2が豊富な食品を日常にとり入れること。代表的なものには納豆、チーズ、ほうれん草、ブロッコリー。
注目は「プルーン」のパワー。1日5個のプルーンを習慣に
特に注目すべきは、2022年10月に報告された研究。閉経後の女性が1日5〜6個のプルーンを食べるだけで、骨密度が大幅に向上し、その効果が長期的に持続したことを発表。これは、これまで便秘改善のイメージが強かったプルーンに「骨を強くする」という美容効果もあることを実証。

ちなみにこの研究はプルーンの会社が資金提供していますが、結果として骨密度向上には5〜6個で十分であり、それ以上食べても効果に大きな差はないというデータ。ただし、プルーンは糖分も多いため、食後のデザートとしてではなく、おやつとして摂る時間帯を意識するなど工夫が必要。
【鉄則③】
顔の骨に「適度な刺激」を与える
骨は、物理的な刺激が加わることで新陳代謝が活発に。特に顔の骨は、咀嚼や表情筋の動きによって刺激を受けています。

2003年に『Journal of Oral and Maxillofacial Surgery』に掲載された研究。顎に継続的な刺激を与えることで、骨密度が維持されることが報告されており、これは硬いものを噛んだり、よく噛んで食べたりすることが、顔の骨を丈夫に保つことに繋がることを示しています。
「柔らかい食事」が骨委縮を早めている?
パン、パスタ、柔らかく煮込んだ料理など、現代はあまり噛まなくても済む食事が増えたことで、私たちは意識しないうちに顎の骨への刺激を減らしてしまっている状態。これにより、顔の骨の新陳代謝が鈍り、骨萎縮をさらに加速させているということも考えられます。
今日からできる「噛む美容習慣」
1.一口30回を目標に。これは「噛む」ことの意識改革です。ある歯科大学の研究によると、咀嚼回数が増えることで、唾液の分泌が促進され、消化を助けるだけでなく、顔の筋肉が活性化されることもわかっています。
2.「噛みごたえ」のある食材を選ぶ。ごぼう、きのこ、ナッツ、根菜など、食物繊維が豊富でしっかり噛む必要がある食材を積極的に食事に取り入れてみて。
3.「ながら食べ」をやめる。スマートフォンを見ながら、テレビを見ながらの食事は、無意識に咀嚼回数が減りがちです。食事に集中し、一口ひとくつの「噛む」動作を意識することが重要。
注意が必要「マッサージ」
顔の骨格に沿ったマッサージは血行促進に有効ですが、間違った方法で行うと肌に過度な摩擦を与え、かえってたるみを進行させてしまう可能性もあるので注意が必要。

ポイントは「顔の骨を労わるように」マッサージすること
摩擦を防ぐために、必ずマッサージクリームやオイルを使用し、指の滑りを良くした状態で行うこと。そして圧は「優しい圧をかける」こと。力を入れてゴシゴシ擦るのではなく、骨に沿ってゆっくりと、優しく圧をかける。
あるいはリンパの流れに沿って「流す」くらいでも効果はじゅうぶん。老廃物を流すようにこめかみや耳の下に向かって優しくマッサージすることで、むくみ対策にも繋がります。
「骨」をケアすることが未来の自分への最高の投資
あなたの美容習慣に今から「骨ケア」という新しい視点を加えることで、表面的な悩みに惑わされない、根本からの美しさを。

未来の自分の顔は、毎日の習慣の積み重ねによるもの。「そうはなりたくない!」という思いをもって、今日からできる小さな習慣から始めてみて。
(参照)
Aesthetic Surgery Journal, 2011, “Aging of the Periorbital Region”
日本骨粗鬆症学会, 2016, 「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」
Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2015, “Vitamin K2 and Bone Health”
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 2003, “The effect of masticatory stimulation on the mandibular bone”
老化の進行を防ぎ劇的に若返る方法は?
≫【5年後に手遅れにならないための」 変えるべき習慣